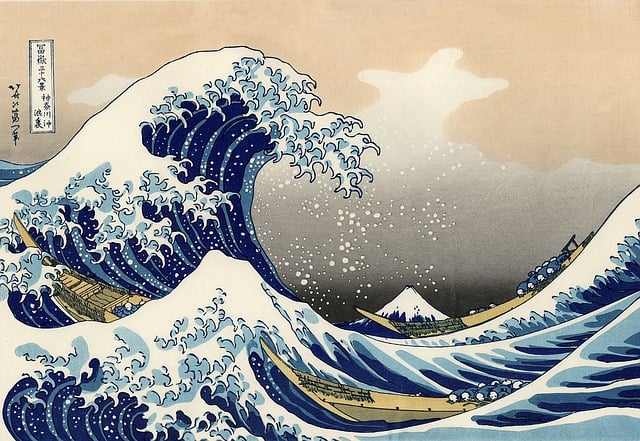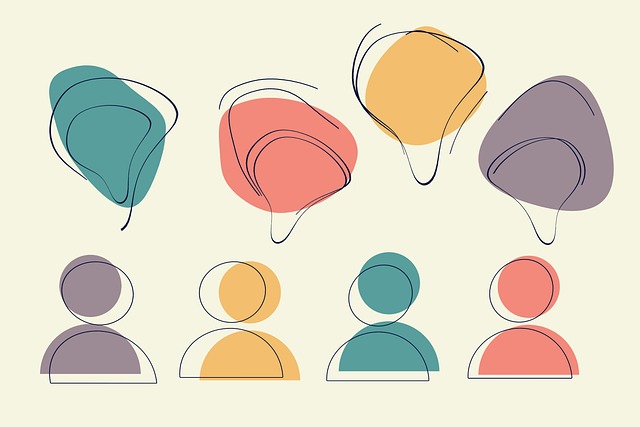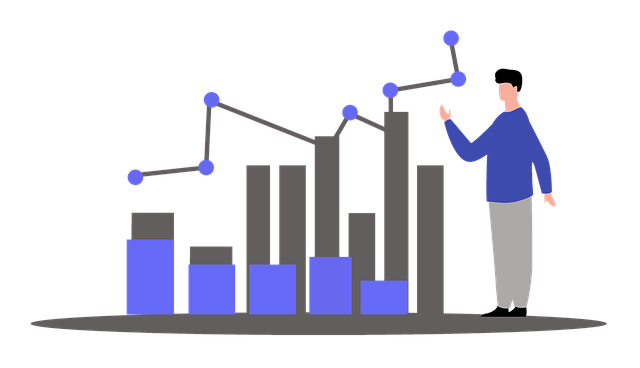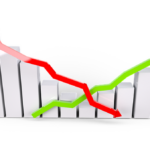ノーベル物理学賞の対象としての機械学習
今年のストックホルムの物理学賞に、機械学習の分野への貢献に対してジョン・ホップフィールド氏と以前グーグルにも所属していたトロントのジェフリー・ヒントン氏が選出された。
ACM、チューリング賞なら自然なのだが、コンピュータサイエンスの分野から物理学賞として選ばれるのは珍しい。ストックホルムの賞は物理学と化学と生理学の3種類しかないので、物理学的な考えがアルゴリズムに導入されているので物理学という枠組みが適用されるのであろう。それだけ機械学習の社会へのインパクトが大きいということの表れと言える。
半導体の微細加工技術が進歩したため、大規模なニューラルネットをシリコン上に効率よく実装することができるようになった。
これは10数年ほど前に、ニューラルネットのアルゴリズムをGPUの演算で実装し始めたことで発生したブレークスルーである。
以前、Thinking Machines社がコネクション・マシンという、従来のベクトル型とは全く異なる並列処理アーキテクチャのスーパーコンピュータを製造していた。現在のGPUベースの情報処理は、当時のコネクションマシンをさらに大規模化してシリコン上に実装しているようなものだ。
ニューラルネットの機械学習アルゴリズムとGPUを使った並列システムは、まさにイノベーションである。最新アーキテクチャのチップは、数万の物理的な演算ユニットを4ナノプロセスの微細加工技術でシリコンのダイ上に実装し、20ペタ flopsの演算能力を持っている。大規模言語モデルや画像のオートエンコーダなどの生成AIは、このハードウェアを使ってCNN(Convolutional)やRNN(Recurrent)、self-attention モデルといったニューラルネットワークを駆動している。
巨大企業がその収益構造故に衰退していく様は、最近のデータセンタービジネスの急速なAIシフトにより主要なプレイヤーが入れ替わっていることからも如実に見ることができる。これは現在進行しているイノベーションのジレンマの一つとみなせる。
随分前のことだが、クリステンセン氏の「Innovator’s Dilemma (邦訳:イノベーションのジレンマ)」を初めて読んだ頃、この概念を国レベルで拡張したらどのような知見が得られるだろうと、当時の日本の現状について考えたことがあった。
そのイノベーションについて国レベルへ拡張して論じているのがクリステンセン氏らの共著による「The Prosperity Paradox(邦訳:繁栄のパラドックス)」である。経営論の枠組みを超えて、社会システムの持続的な発展に寄与する市場創造型のイノベーションについて論じている。2019年の5年前に出版されていたものだが、機械学習における現在進行中のイノベーションのジレンマを目の前にし、彼の近著に目を通しておくことにした。
最近、パラドックスを含む市場の動向についてエッセイ(「外国為替平衡操作のパラドックス」)を著し、パラドックス繋がりで未読だった著書に改めて注目することになった。著者らは発展途上国を対象に、市場創造型のイノベーションをテーマにしているが、内容を吟味すると、日本が埋没した総需要が不足した経済にもこの型のイノベーションが有効であることが理解できるだろう。次項にそのレビューを記す。
書評:The Prosperity Paradox. How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty
Clayton M. Christensen, Efosa Ojomo, Karen Dillon
評者は「外国為替平衡操作のパラドックス」において、因果性がなぜそれほど重要であるかを解説した。本書の著者らも、本書において、現象や状況の相関ではなく、因果性の分析を彼らのアプローチの中心に据えている。
何が何の原因となり、そしてなぜそうなっているのか?
問題をフレーム化するのに、著者が実行している最も良い方法は、最も実用的な回答を得るための正しい問いを行うことである。そのために、彼のアプローチの核となっているのは、単に理論的なフレームワークを適用するのでなく、実際の疑問に焦点を当てることである。
国家の長期的な趨勢について、クリステンセン氏自身と共著者らの視点には以下のようなものだ。
持続的な繁栄のためには、市場自体がないところに需要を創造し市場を新規に生み出すこと。著者らの主張では、市場創造型のイノベーションは、繁栄の好循環をもたらすとしている。
アフリカを例に、慈善事業による井戸とモバイル事業を比較している。井戸の故障時、修理する資源がないため、繁栄が持続しない。モバイル事業では雇用とインフラの整備が進められ、社会全体の生活様式も変化し、長期益な繁栄の循環をもたらす。
著者らの分析による提案は、イノベーションによって需要を引きだすことである。”買えない・買わない”が巨大市場に変わる。
途上国ではこうした成功例を数多く見ることができ、著者らが事例を提示している。
安藤百福氏の発明とされる、インスタント麺は、現在ナイジェリアで年間45億食売り上げているらしい。インスタント麺を知らなかった人々に、それを紹介して販売した現地のアントレプレナーたちによる、何もなかったところに新しい市場をイノベーションした市場創造型のイノベーションである。食文化を変え、文化や生活様式に影響を与えていった。
本書はシンボリックな引用で始まる。印象深いので抜粋する。
20年前にアフリカでテレコミュニケーション・ネットワークの構築を試みた人物の逸話である。
彼がテレコムサービスをアフリカで始めようとしたとき、真剣に人々は彼を笑い、プロジェクトは絶対に成功しないと言った。男はチャレンジングなことだとわかっていた。しかし、なぜ彼らには機会が見えないのだろうか? ーMO IBRAHAM
Ibraham氏は新しい市場を創造するチャンスがわかっていた。彼は、アフリカ全域にモバイル通信会社を作ることをゴールにCeltelを設立した。彼は、元ブリティッシュ・テレコムにいたビジネスマンで、現在、Celtelはアフリカの複数の国に跨ったテレコミュニケーション・ネットワーク・サービスを提供している。
著者らは、様々な形態の国において、イノベーションへの投資、もっと特徴的には市場創造型のイノベーションが、世界中の国々で繁栄への確かな経路であることを示しているのを見つけている。
この過程を通れば、貧しい国が100億ドルの価値の富、100万の仕事を市民に創造することができた。
市場創造型のイノベーションへ投資する機会を見つけること。そして地域経済の成長を助ける発展のPull 型ストラテジーを実行する。
これらの考えとテーマの全てが繁栄のパラドックスを解決するのに極めて重要であることが、イノベーションを通した異なる視点から、繰り返し、調査することで理解できるだろう。
イノベーションの定義は、組織が労働、資本、材料、情報を価値の高い生産物とサービスに転換することによる、過程の変化である。
成功する市場創造型のイノベーションは、特別な三つの性質をもつ。
発展の過程での汚職
制度は、最善の意図で新興国に導入されたが、なぜそれほど多くのPush型の制度が新興国の経済で、効果なく、悪化し、破綻したかの理由となった。私たちは法律、システム、制度では問題を治すことができなかった。
効果的な制度は単に規制やルールに関するものではない。最大の制度は、その地域に住む人々がどのように問題を解決し、発展させるかの文化に関するものだった。それらの中心となるのは、人々の価値を反映したものだった。
イノベーションはこの過程で重要な役割を演じることができる。
どれほど制度の再構築が善意から出たものでも、もし、できる限りその地域に住む多くの人々を養う市場に繋げるか、または市場を創造するイノベーションにつながらなければ、それを持続可能なものにすることはできない。
それでは制度の導入を、もっと効果的に実施するにはどうすれば良いだろうか?
著者らはその回答として以下の三点を挙げている。
腐敗の性質と三つのフェイズ
本書には なぜ腐敗は「雇用」され続けるのか という章が設けられている。
なぜ、多くの人々が腐敗に従事することを選択するのか?
著者らは、以下のような構造的な性質を指摘している。
- 社会の個人の多数は、発展することを望む。雇用を探す貧困者から、さらにステータスを得ることを探す富裕者に、私たちの多くは金融、社会、心理的な富を解決することを望む。良い学校、良い休暇、礼拝の地に赴く理由である。また、貯金し、家を購入し、ビジネスを始める理由でもある。それらを発展させるために社会に合法的なオプションが少ないならば、汚職は、より魅力的になる。
- 社会を構成する人々が共通に持つ発展を求めるモチベーションに従い、違法を取締る側が、自身が所属する集団内部の違法行為に対して寛容であれば、汚職は蔓延することになる。これは途上国と同様に取締る側の現象と言える。先進国といえども、法曹界や司法側の中立性が担保されていなければ、日本のように汚職は蔓延するのである。
- すべての個人、企業はコスト構造をもつ。腐敗防止プログラムが、収益ーコストの式に基本的に影響しないならば、それらは持続可能ではない。どこかの国の司法警察の収入が支出より少なければ、汚職に感染しやすい。生活を支配する環境が、生存選択を難しくする。
- 多くの個人が、彼らの自身の利益を得て発展させるために、広く行き渡っている法律の影響を、覆すストラテジーを探す。(ハーバードのEdword Glaeser とAndrei Shleifer、は20世紀の規制に関する研究によれば、)人類は生来、所与の環境の中で彼ら自身に対して最も良い選択をするらしい。
経済発展の過程で、腐敗には三つのフェイズがある。
(1)公然の予測できない汚職、=>(2)隠された予測可能な汚職、 =>(3)透明性のある社会と呼ぶものへの転換。
私たちは、できる限り、信頼と透明性が価値を持っている社会、第3のフェイズに近づくことを望んでいるということを仮定している。
【フェイズ1】公然の予測できない汚職
貧しい国の多くで見られ、政府の制度は信用するのが難しく、汚職が蔓延している。
民主化を進めようとしたアフガンやイラクでも起きていたことだが、民主的政権として新設した管理組織にも汚職が蔓延する。
【フェイズ2】隠された予測可能な汚職
予測不可能から予測可能への転換は、経済的、政治的に高価になる。第一に、法律ではなく市場の創造を必要とする。
多くの人々は、彼らがしていることを、すべきでないことであるとわかっている。新しい法は、何をするか、いつ政府が法を執行する能力を持つか混乱がある時にだけ、問題を解決するのに役立つ。
中国をはじめとする国で、当初、法を使って汚職を根絶しようとしたが、ほとんど成功しなかった。逆説的に、より多くの法が汚職と戦うために制定され、より多くの汚職を拡散させたようだった。例えば、中国では汚職に対して1200以上の法、制度、規制がある。
一方で、汚職の蔓延にも関わらず、海外からの投資は進展した。なぜ、彼らは投資する前に、中国が汚職を根絶するのを待たなかったのか?
最初に中国の汚職の種別が、第一のフェイズにある他の国とは異なっていたためである。それは、隠されており、予測可能だった。
予測可能なためビジネスを行うコストの計算をすることができる。
該当国がまだ透明性のある社会ではなく、またその途上にあることは、私たちのすべてが認めている。発展が長期にわたって持続可能になるためには、国家は第3のフェイズに転換しなければならない。
【フェイズ3】透明性
米国ではウッドローウィルソン時代、汚職は深刻で拡散され、主要なインフラ・プロジェクトの隅々まで行き渡っていた。
著者らの理解として、人々が生活を改善するために汚職に従事する場合、汚職と戦うための努力の全てに焦点を当てるのでなく、私たちがコントロールできるものに焦点を当てることを提案している。
人々が従事できる何か代わりのものを供給することなし、汚職は、最小化させるのが、信じられないほど困難となる。
一旦、十分な市場が創造されると、人々はその市場の成功に感心をもつ。より多くの組織的なビジネスモデルが実現されると、組織が汚職を減少させなければならない、より多くの機会が発生する。
単純に新しい法の制定は、または単に厳しい罰則は、彼らの振る舞いを変えさせない。それはちょうど汚職を地下に潜らせるだけになる。
市場創造型のイノベーションは、汚職の状態や制度の存在に関わらず、必要なものを牽引する能力がある。
市場創造型イノベーションの原理
貧しいコミュニティに提供される多くのインフラ計画は、インフラの建設と維持を整えるのに十分な価値を分配、蓄えることなく、それを維持するのに十分な利益を生み出さずに忘れさられる。
もし、分配、蓄積するための価値が、インフラの開発と維持のために蓄積されなければ、インフラ計画はほとんど失敗する。
信じられないことにそれが発生し続ければ、貧しい国は大規模なインフラ計画の基金のために借金を繰り返し、それらの債務のサイクルから抜け出せない。2018年3月にIMFは40%の低所得国は、債務のサイクルにあるかまたは、非常に高くそれに陥りやすいと報告している。
しかしながら、インフラの開発がイノベーションと新市場の創造によって社会に引き寄せられるとき、投資はもっと成功可能なものとなる。突然、インフラ開発の高いコストは、もっと管理可能になり、そのコストはしばしば、創造された新市場の生み出す利益によって内部で賄われる。
政府が意図する前に、創造的な起業家とイノベーターが、ビジネス上の必要性でインフラを創造するためのより早い経路を見つけていることは、完璧な例として歴史が示している。
米国では初期の道路、鉄道、運河を作ったのは、起業家と私企業である。これらの会社では、株式と社債がこれらのインフラ建設の基金となった。電線網や通信網も同様である。
あなたが新しい市場を創造するとき、市場からの利益がインフラストラクチャの効率的利用を牽引するための支出を助ける。それを効率的に利用することの牽引は、長期的に、より強化される可能性が高い。
繁栄のパラドックスを繁栄の過程に変えることが重要である。そのための市場創造型イノベーションの原理を以下にまとめる。
国の繁栄と腐敗
日本の特異な状態は需要不足が数十年継続していることである。背景に高齢化社会の進行による消費性向の変化もある。
財政支出により有効需要を作り出し、需給ギャップを埋めてきたが、一時的な需要創出のため持続性がない。これに対して市場創造型のイノベーションは持続的な循環をもたらすという。
鳴物入りで導入された経済政策としての大規模金融緩和が、意図した成果をあげられなかったのは、因果分析がなく、まず最初に”3本の矢ありき”から始まっているためであろう。3本の矢の一本として、為政者への忖度を動機づけとした必要ない過度の金融緩和が実施されてきた。政治的な意向によって前総裁の就任前から金融緩和に強いインセンティブが働いていた。
現実は借りやすくしても、資金需要がなければ貸出に繋がらないため、貨幣の流通速度は上がらない、取引需要は伸びない。事業主にとっては投資対象があれば、金利があっても借りるものだ。
需要がないところで投資や消費は伸びず、貨幣の流通は増加しないため、景気の好循環とその結果としてのインフレにはならない。
企業や家計の総需要の不足が貨幣供給によっては解消しないという、金融緩和を大規模化する前から予見されていたことが明白に実証された事例となった。十分な低金利下においては、金融政策で物価を上昇させることはできない。(注1)
さらに賃金上昇がないのは、賃金を上げなくても労働力が確保できるからである。雇用環境として非正規雇用が常態化しており、特別な技能を必要としない人手としての需要が財政支出によって作られてきた。非正規雇用は全体の4割に達しており、雇用主側からは簡単に契約が解除できる仕組みになっている。法の運用上の要件を避ける形で、二重派遣は公然と実施されており、この業界では中間マージンが多重に搾取されているケースが多い。非正規の可処分所得は低いため、家計の消費が景気を牽引することはない。
特別な専門知識を要する、例えば、いくつかの国でイノベーションを起こしているAIの分野では賃金を上げて人材の争奪が発生するが、日本では、そうした産業は全くといっていい程育たなかったし、現在も育っていない。
これは情報通信だけでなく、他の産業分野でも同様である。
多くの事業主は、安い労働力が調達しやすくなった一方で、イノベーションを起こすような分野への投資が欠落していることに関心がなかったとも言える。
対照的にAIを牽引している国外のテクノロジー企業は、データセンターの電力消費を補うために核融合発電などの電力事業への投資も増やしている。これはPull型イノベーションの典型例で、新しいサービスの創出が波及してインフラ投資が進み繁栄が循環する仕組みになる。
国内の需給ギャップを埋めるための財政支出により、深刻な不況に陥ることはなかったが、新市場を作り出すイノベーションを起こす分野への投資にはつながってこなかった。
ここで取り上げた著書の執筆者らは、市場創造型のイノベーションが慈善事業型の需要創出より、需要のないところに消費を生み出し、持続的な繁栄をもたらすものだと喝破している。
繁栄のパラドックスから繁栄の過程への転換は、需要のないところに需要を創造することで経済成長に導くことである。
著書の前半で解説されているように、その国内での多くの活動にも関わらず、国家の繁栄が解決されないとき、国家は成長の問題を持っているのでなく、イノベーションの問題を持っているかもしれない。
途上国での井戸の開発などは、政府開発援助(ODA)の紐付き経済的援助の多くが陥る失敗例として評書でも挙げられている。この数十年間こうした経済的援助の失敗例を国内でも実施してきた。需給ギャップを埋めるための財政支出は、国内への経済的援助事業だった。数十年間のデフレ下で、私たちの国は非常に効率の悪い財政支出をしてきた可能性がある。つまり、そこには、ODAに4兆ドル(400兆〜600兆円)以上費やされても、貧困がなくならないのと同じ理由と構図が横たわっているのが見えてくる。
従来の財政支出は、持続的な成長に寄与していない。支出の中身は、Pull型のイノベーションへの投資に向けられたのでなく、押し付けられたインフラ投資だった。途上国への経済援助の失敗例と全く同質なのである。
‘金融緩和をどれほど実施しても、需要がないことが問題なので、政府が積極的に財政支出を行い需要を創れば良い。緊縮財政が問題だ’という主張が一部にある。
しかし、それでは一時的な需要は生まれるが、多くの途上国へのODAと同じ構図で、持続的な成長には結びつかない。多くはPush型のインフラ投資であり、押し付けられたインフラはやがて使用されなくなり放置される。
またインフラ投資と腐敗の関係で言えば、あたかも経済政策とみなされている外為市場介入には、常に”内通者による振込詐欺”(注2)という汚職がセットになっていることを忘れてはならない。
私たちは常に、コントロールできるものに焦点を当てなければならない。汚職が発生する機会を減少させるために、国際化、統合化させることで、組織自身が汚職を実行する機会を減少させなければならない理由が発生する。
現行法では大臣権限で外為市場に介入することが可能であるが、これを是正するには市場介入の機会自体を減少させ、そうした機会を減らす必然性を組織が持つようにしなければならない。
外為市場経由の振込詐欺の実行者に忖度するなど、愚の骨頂であるが、ジャーナリズムが機密費から賄賂を受け取る状況が常態化してしまうと、国民に実態を知らしめる機能は働かない。汚職は深刻に拡散されていくが、汚職社会の行き着く先として、いつかは透明性のある社会を実現させるための歩みを止めてはいけない。それこそが発展が長期にわたって持続可能になるための経路である。
そのためにはできるかぎり公的予算の分配先での執行に関して透明性を確保するための担保が一つでも多く必要となるだろう。