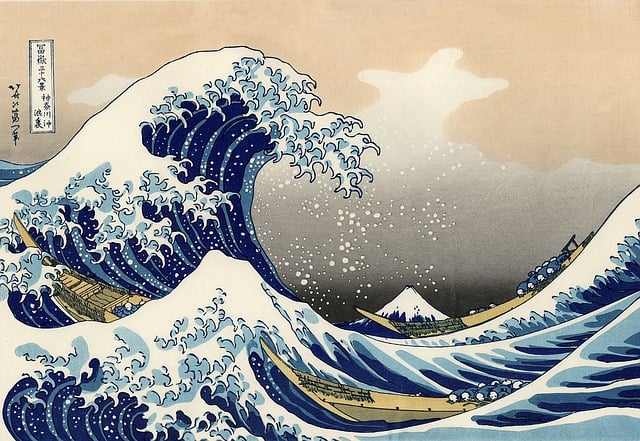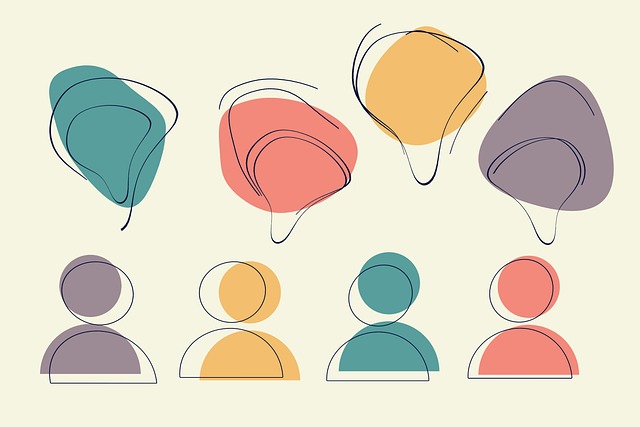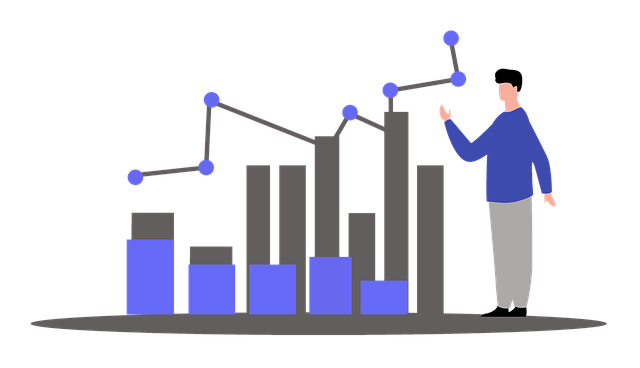The Economic Weapon
The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War.
Nicholas Mulder
The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War
1914年、第一次世界大戦から第二次大戦の終戦と国連の誕生する1945年までの30年の経済制裁、封鎖についてのリサーチです。2022年に出版され、いくつかの経済、外交専門誌でその年のベストブックに選ばれています。
最近(2023年)の東欧の情勢を分析する上で、これに対比して、帝国主義時代の日本と欧州のいくつかの国への経済制裁について深く知りたかったので読んでみました。
1世紀前の時代背景ですが、当時の日本のメディアはプロパガンダに染まっていたため、その点では現代のロシアと共通しています。時代を超えて周辺国の国際関係と国民のメンタリテリティに同じ傾向がありそうなことは推察できます。
サブタイタイトルにthe rise of sanctions as a tool of Modern warとあるので、戦争の道具としての制裁の台頭、武力に対抗する手段としての経済制裁の始まりと言えるでしょう。
著書の内容は3部構成で、1部は大戦前の英仏による経済制裁の起源、2部は第一次大戦から1931年の満州事変によるグローバル危機の直前まで、3部が大恐慌から第二次大戦へ30年台から40年台の危機の間の経済制裁について、関係諸国の経済、社会状況と軍事行動、外交、為政者の対応として経済制裁が詳細に記されます。
この著書を書くにあたって、多数の文献にあたっていることが脚注からわかります。脚注のノートだけで著書の1/4の100項ほどあります。丹念にリサーチされた内容なので興味深い箇所は、脚注からさらに参照元を当たれば良いでしょう。
経済制裁の起源は、セシル(英)とブルジョワ(仏)が進めた1919年パリ講和会議になります。
背景にある国際間での資源、情報の流れ、需給と市場シェアが示されます。例えば、UKが石炭時代のサウジアラビアだったこと、マンガンの消費がドイツに集中していたことが示されます。十分な石炭と食糧の輸入がなかったロシアでは、ロシア革命が発生します。
食料の多くを自給していたドイツの農業従事者は戦闘に従事することになった結果、農業生産量が1/4になり、経済封鎖によって飢餓状態に陥ります。
セシルにも助言していたパリ講和会議に参加していた若き日のケインズは、経済制裁(economic wepon)は、deprivationより、provisionに焦点を当てるべきだと信じていました。
ドイツのライン地方(Rhineland)への侵攻によりフランスの経済制裁は始まりますが、1920年代のドイツの西ヨーロッパでの軍事力の再現に対して、近隣の大国による攻撃にさらされるフィンランドやポーランド固有の事情や生存戦略は、興味深く、現在のNATOとの関係にも通じます。ポーランドは生存のために、西側の支援としてフランスやチェコと協定を結びます。
飢餓は中央ヨーロッパでの社会秩序を壊し、当時台頭した独指導者の思想の一つLebensraumの概念にも繋がります。
国際連盟の経済制裁には、飢餓封鎖(hunger blockade)も含まれていましたが、フーバーだけは、敵国の市民に対する飢餓は、今後は武器にはしないと考えていたようです。しかしこの食料の除外は欧州の主要な列強には受け入れられず、ロンドンの会議で多国間協定として海軍軍縮条約は成立しますが、フーバーの提案は当時の英米のライバル関係を浮き彫りにして却下されます。
この時代の経済封鎖は、次のように端的に示せます。(以下、本文より抜粋)
Mulder, Nicholas. The Economic Weapon (p.11). Yale University Press. Kindle 版.
The internationalist search for more effective sanctions and the ultra-nationalist search for autarky thereby became locked in an escalatory spiral.
このautarkeyは、当時のドイツの防衛的自給自足(Verteidigungsautarkie) や無料の原料(Rohstoff-Freheit)という考え、イタリアの経済自立政策(piani autarchici)、日本のyen bloc(共栄圏)というブロック経済圏への指向であり、ロシア革命後のソビエトの拡大と大戦後の東西経済圏の分断へと進みます。同様に現代のロシアがユーラシアユニオンや多極化した世界を指向しているのは指導者の演説から、この時代と同じ傾向が読み取れます。
第3部の鍵となる満州に関する危機時、日本の対米貿易比率は40%に達しており、米国の対日輸出は4%に過ぎませんでした。輸出入と金融取引の制限による経済制裁は強力に効果を発揮しますが、それが開戦を招くかもしれないという目算はなかったようです。
しかし現代の私たちはよく知っているように、当時、東京では数度のクーデター未遂が発生し、軍の予算を削減しようとしていた高橋是清などの国際派がいなくなり、軍部への歯止めは効かなくなります。
ABAは米国内全域で日本のボイコットのキャンペーンを始めます。
リットン調査団の報告後に、日本は撤退勧告案を可決した国際連盟を脱退しますが、同時期、欧州ではナチスがドイツで台頭します。
著書は、経済制裁という切り口による関係各国の社会状況が、詳細に把握できる内容です。
イタリアのエチオピア侵攻に関連して、ソビエトもエネルギーとインフラの面でイタリア、ドイツへのオイルのエンバーゴに参加します。USAは中立の立場でしたが、後にオイルのエンバーゴに参加します。同時期にドイツがベルサイユ条約に反してライン地方に軍隊を進めます。東アジアと欧州の当時の緊張状態がわかります。
USAは1940年7月に経済制裁の歴史に加わり、日本とスペインへのオイルと鉄の輸出を止めます。これは平時に経済制裁を実施する初めてのケースになります。
1940年時点での主要な産油国であるUSA,ソビエト、ベネズエラ、イラン、オランダ東インドで世界の産油量の87%を占めていました。イランのオイルはほぼUKの管理下にあり、ベネズエラとイランのオイルはUKとオランダの管理下でした。東京から見ると開いている調達先はソビエトだけでしたがサハリンの産油量では十分ではありません。
ルーズベルトのスペインへの禁輸は、欧州での"オイルの飢餓"を目的としたUKの戦時経済政策の効果を強めます。これを受けたドイツはウクライナとロシアの資源に目を向けることになります。
この著作が題材にしている時代のロシア革命、ファシズムの台頭は飢餓によるものです。日本では関東大震災と昭和金融恐慌、その後、東北地方が大凶作に見舞われます。当時日本国内では、満州を日本の生命線と主張していました。
史実に基づく傾向として、飢餓はレジーム転換の契機になります。古代から近現代まで多数の事例があります。
中国の漢王朝は、末期に黄巾の乱の発生と混乱を契機に終焉します。飢饉による王朝側の備蓄米の放出は、漢の役人の汚職による横流しのため、民衆には行き渡らず、黄巾の乱が発生します。
江戸幕府の終焉も、飢饉が契機です。飢饉により幕府側の備蓄米の放出は、漢と同様に役人の汚職による横流しのため民衆には行き渡りませんでした。飢饉と汚職を背景に大塩平八郎の乱が発生し、そこから最後の将軍を出した水戸藩の改革派による桜田門外ノ変、明治維新へと進みます。フランス革命も同じ構図です。イラン革命によるパーレビ体制の崩壊も、役人の汚職と民衆の飢餓を背景に発生しています。
飢饉がレジーム転換の契機になるのは、生存への欲求が行動に反映されると考えられます。時代や国境に関わらず人が作る社会システムは、その社会を構成する人々の生存が脅かされると破綻し、生存への欲求が行動に反映され、レジーム転換に結びつきます。
著書でリサーチしている時代の経済制裁は、殺傷兵器を使った武力行使に対抗して、武力を行使することなく、対象国に資源や食料の供給を止めることで飢餓が発生する面があります。制裁に参加する国、協力する国が多ければ、孤立化と経済制裁の効果は大きくなります。
現代の制裁は人道的な側面が無視され、食料の供給が停止されることは表面上ありませんが、東欧ではオデッサの穀物サイトの破壊や港の封鎖は、食料をめぐる封鎖が手段の一つであることを目にします。
現代の政策担当者やビジネスマンが当時の制裁から学ぶことは多いでしょう。
100年前の30年間の経済制裁の歴史を踏まえて、現代の日本の30年
グローバル化がコストを下げるのとは逆に、デカップリングはコストを上昇させます。これは貿易に関わる双方に対して言えることです。
東西冷戦が終結した後、生産コストが下がります。同時期、日米貿易摩擦の影響で、日本が通信と金融を自由化することで、市場開放を進めた結果、、流通障壁が減少し、物の値段は急速に安くなりました。バブル崩壊後の日本では経済のグローバル化に伴い、デフレ経済が定常状態になります。数十年にわたる日本のデフレは、バブル崩壊、東西冷戦終結、国内の規制緩和と自由化という同時期に起きた出来事ともに始まりました。
東西冷戦が終結する前、日米貿易摩擦を背景に日本国内では土光臨調と前川リポートをもとに内需拡大が叫ばれていました。しかしながら当時から数十年に渡り需要不足の状態は持続しました。この間ビジネスに関わっていた人たちは、実体験としてそのことをよく知っているでしょう。バブル崩壊の後遺症としてのバランスシート不況、冷戦終結による東側諸国、中国の市場経済への参入がありました。自由貿易の恩恵はコストがドラスティックに下がることです。その状況を現代に生きる私たちは実際に経験しています。
経済制裁、封鎖はこれと逆の作用をもたらします。米中間で起きた個別の関税の応酬も貿易制裁としてみると、自由貿易の恩恵と逆の作用を与えます。多方面でのコストの上昇です。
ウクライナへの侵攻に伴う逆作用の結果によるグローバルなインフレーションが、30年継続した日本のデフレーションを止めています。デフレーションは、総需要の不足であり、貨幣の流通量を調整する金融政策だけで物価が上昇しないことはわかります。金融政策は資産デフレによる不況には効果があったとみなせるかもしれません。それに関して総括した検証例があれば紹介したいと思います。