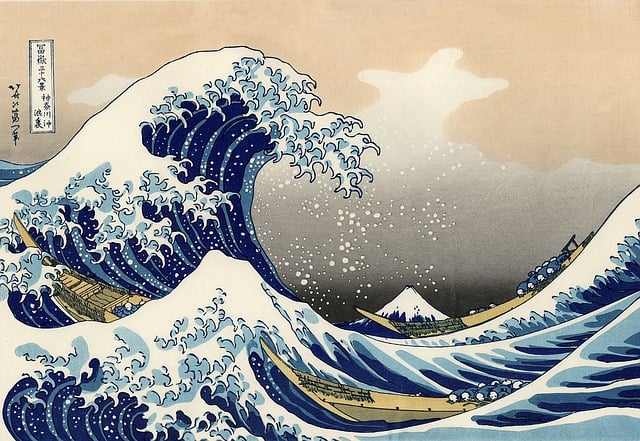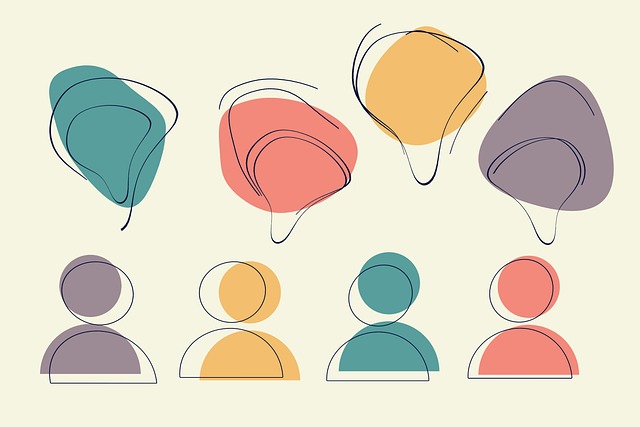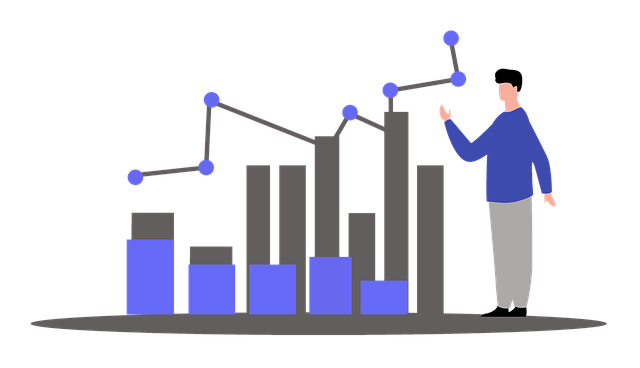Eighteen Days in October: The Yom Kippur War and How It Created Modern Middle East
Uri Kaufman
2023年11月現在
中東での紛争の拡大懸念が緩和したことで原油価格が$80を切リました。前回もそうでしたが、原油価格が$80を切るとOPEC+が減産を決定するようになりました。
中東産油国が最初にエンバーゴを始めたのが第4次中東戦争の時でした。当時はOAPECでしたが、これを契機に石油の価格支配力はメジャーからOPECに移っていくことになります。
このOPECが石油の禁輸を実施した第一次オイルショックから50年が経過しました。第4次中東戦争は、ユダヤ教の贖罪日に起きたためヨム・キブール戦争とも呼ばれます。1973年10月6日のことです。
現代の、2023年10月7日のハマスによる奇襲は、それから50年後のこのヨム・キブール期間、再びユダヤ教徒にとって宗教的な祭日に発生しています。
原油価格の動向および中東問題を把握する上で、ヨム・キブール戦争に関して不足している知識を補うために、この著作を読んでおくことにしました。
この著書は2023年9月に出版された歴史書です。
Eighteen Days in October: The Yom Kippur War and How It Created the Modern Middle East
1967年6月9日、第三次中東戦争後に、エジプトのナセルは言っています。どれほど時間がかかろうとも、帝国主義が一掃され、イスラエルが一国になった時、レベンジの日が来るだろう。
開戦前、シリアは、エジプトなし戦争を実施するつもりはなく、エジプトでは、イスラエル空軍が無力化されるまで戦争には向かわないと考えていたようです。1973年8月21日シリア軍の関係者はエジプトのカウンターパートに会うためにアレクサンドリアに向かいます。
そして10月の18日間の出来事がそれぞれの当事者達の行動を通して、その期間に事態がどのように進行していったか、その時、そこで何が起きていたかが記されています。シリア、エジプト、イラク、イスラエル、ヨルダン、米、ソビエトの各関係者の発言が引用されています。
当時はアラブ側をソビエトが支援していたため、米ソの対立も一つの背景として存在しています。この時期、米中国交樹立の後、ベトナム戦争は停戦されてます。その後、中東でこの問題が勃発します。
その日、事前に計画を掴んでいたイスラエルは、アラブが攻撃してきた際、反撃する計画を立てていました。
しかしながら、空軍はシリアのSAM(スカッドミサイル:ソビエト製の地対空ミサイル)によって想定外の大きな被害を受けます。最初の72時間で49機の航空機と500台の戦車を失くすという、初戦の戦況から核の使用が検討されます。
読者はその場に居合わせているかのような臨場感で、事態の推移を追い、何が起きていたかがわかります。
戦況は日々変わりますが、USAの国務長官もイスラエルへの支援とともに、関係各国へのシャトル外交を続け、エジプトを交渉により停戦させ、後のキャンプデービッド合意に結びつけます。
一方、イスラエルを支援するUSAとオランダに対し、OAPECを形成するアラブの産油国6カ国は、石油のエンバーゴを開始します。
著者は多くの関係者への取材により、当事者の考え、発言を通してこの時の一連の出来事を各当事者の視点で記しています。当時の事態の推移を把握できる良い資料です。
この18日間で、現在のエネルギー需給に関わる資源のパワーバランスが大きく変わることになりました。
50年後の節目に起きた出来事で、改めて当時、発生した出来事の重要性が認識されます。
同時代の日本
日本では、列島改造論で圧倒的な支持を受けていた田中内閣は、オイルショックとそれに伴う物価上昇に不満を持つ国民の煽りを受け原発推進に舵を切ることになります。東日本大震災で事故を起こした福島の原発建設もこの頃計画されていきます。
現在から振り返ると、この政策転換もショックドクトリン(注)の一つとみなせるでしょう。
(注)
The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.
Naomi Klein