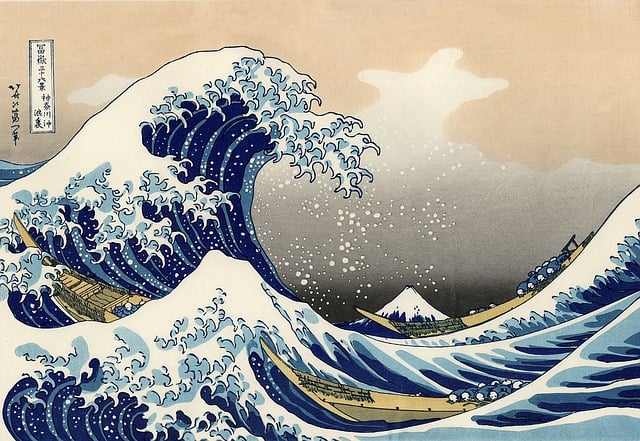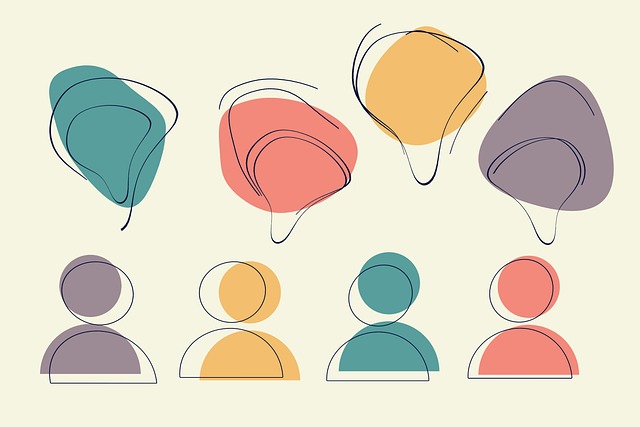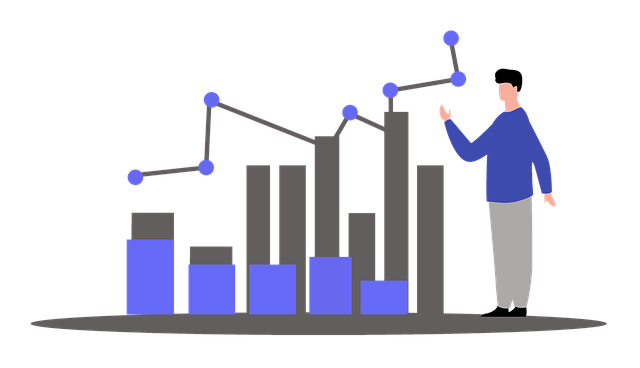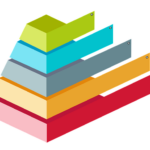Chokepoints: American power in the age of economic warfare
Fishman, Edward
経済制裁は軍事的な脅威に対して兵器を用いず、経済的な影響力を行使することで、該当国を制止することを意図しています。本書に取り上げている5つの出来事を通して、為政者の意思決定の相互作用で作られる現代史と、経済面でのUSドルの影響力を把握することになるでしょう。
Chokepoints: American power in the age of economic warfare
以前、"Economic weapon"の書評を載せました。同書と同様に本書は、軍事力を用いずに外交的な影響力を行使する手段としての経済政策に焦点を当てています。イラン、ロシア、中国に対して経済制裁を実施してきたワシントンの経済外交政策のインサイダーによる著書です。
"Economic weapon"は1世紀前の経済制裁の起源に関して詳細に記述されていました。本書は、紛争に対して兵器という莫大な防衛予算を使わない、USドルの力を用いた現代の経済制裁に関する政策について解説してあります。半世紀にわたる経済のグローバル化と新自由主義の再構築によって、世界経済は統合され、合衆国の経済を動かすシステムと信用の力を行使することは世界に影響を与えます。
現在、ウクライナの紛争で、黒海における停戦が協議されています。ボスポラスは古代から重要な地理的拠点であり、沿岸に欧州、中東を含む地中海と黒海を結ぶ海峡です。黒海の航行の安全性の確保は地政学的に重要でした。これは、現代のウクライナとロシアの紛争でもグローバルに複数の国々が影響を受ける海域です。2022年12月5日にロシアはウクライナに対して国境を超えた戦争を始めました。オイルタンカーは、ボスポラスで渋滞するようになっています。
これに対応した制裁の一つとしてロシア産原油へのプライスキャップが実施されました。ロシアのオイルは欧州のタンカーで運ばれますが、その保険は英国が請負、USドルで支払われます。
グローバリゼーションによって、内部統合された世界経済の中ではUSオフィシャルの行動は、呼吸するスピード地球を覆います。
近年のイランの核兵器開発、ロシアの帝国主義、中国の支配に対して、合衆国はその仕事をこなすために経済的な兵器に手を伸ばしました。著者はこの過程で世界経済は戦場なったとみています。その兵器は制裁、輸出コントロール、投資の制限の形態をとります。
合衆国のこれらの戦いの軸の強さは、莫大な防衛予算から来るのではなく、国際金融と技術の卓越さから来ています。本書によると、これは、新しい形の戦争です。
強大な力は、ボスポラスのような地政学的なチョークポイントをコントロールすることによって発展、生存してきました。グローバル化した経済で合衆国の力は、違った種類のチョークポイントに依拠しています。それは、USドルです。国際貿易と金融の実質的な標準の通貨です。
最近、合衆国政府の新しい関税の導入によって、ドルの信任が揺らぐという声が一部にあります。以前から事あるごとにそうした警鐘が現れていました。しかし、実際のところ、その翳りは全くありません。BRICSを中心とした決済通貨の構想などがありますが、ドルに変われる通貨は存在していません。
本書は、近年、発生した5つの出来事に関連して、USドルの力を使った経済制裁について記してあります。対象はイラン、中国、ロシアに関するものです。
中国のZTE社は、合衆国製品をイランに持ち込んでいたことが制裁の対象の理由ですが、ZTE社と国内で競合しているHuawei社は、もっと上手く実行していたようです。Huawei社は5Gネットワークのバックドアの問題もあり、制裁は継続しています。
同社の子会社のHiSiliconはAscendチップを設計しており、同社は、最近ではAIに関する競争相手としても注目されています。深圳一帯に半導体の集積拠点が構築されている報道資料の衛星画像によると、その一帯は、急速に規模が拡大しています。深圳政府の財政的な支援もあって半導体の製造と設備機器の製造が集約され、半導体製造装置のSiCarrier社、 メモリのSwaySure社の拠点もあり、Huawei社との人材の交流もあるようです。
半導体に関して日本ではRapidus社への国の支援などがあります。これと同様のことですが、中国ではHuawei社を中心とした深圳一帯の半導体拠点へ、国と深圳を挙げて大規模に支援しているようです。
本サイトでHuawei社のAIに関する取り組みを取り上げましたが、同社は高速通信技術についても優れたノウハウを所有しています。
本書には中国による5Gのインフラが第三世界を含めて拡大していくことに、合衆国が懸念を強めていた経緯が記されています。
通信技術は軍事技術とも深く関係しており、軍需産業が自国の政府機関と密接に結びつくのはどの国でもあることです。Huawei社の創業者の家族である同社の財務責任者は、複数のパスポートを所持していたようにイランとの取引にも深く関係していたようです。
イランのドローン、”シャハド(Shahed) -suicide drones"はロシア国内にも製造拠点を設けています。米国や欧州、日本製の部品が中国企業を経由して、ロシア国内のイランの軍需企業に持ち込まれていたとしましょう。そこで製造されたドローンが、キエフの住宅を破壊している映像を、現在、私たちは報道を通して見ています。
経済制裁は、参加国が多ければ効果を発揮しますが、第三国を経由した輸出規制品が入ることがあります。イランにはZTE社,Huawei社などの中国政府と結びつきの強い企業を経由して持ち込まれていました。
Huawei社は、現在もAI用のライブラリを開発しているPyTorch Foundationの主要メンバーですが、先端技術の開かれたコミュニティの中では、本書で取り上げるような政治的に敏感な輸出規制の懸念がアジェンダになることはないでしょう。
以前、サウジアラビアの皇太子とイランの元首が握手をしている画像が新聞誌面に掲載されて、少し驚いたことがありました。二人の間の中央に中国政府の王毅氏がいたからです。サウジとイランは長年、宗派も異なることから対立しており、サウジとイエメンは戦争状態にあり、イランはイエメンのフーシ派を支援しています。ところが両国首脳は、中国が間に入って和解します。現在の中国のイランとの深い関係を示す象徴的な出来事でした。
イランの核開発の制裁に関連して、日本のコンソーシアムが手を引いたイラン最大の”アザデガン”油田の開発を引き継いだのが中国でした。その当時から油田開発や原油取引を通じてイランは中国と深い関係を築いています。そうした密接な外交上の関係はHuawei社を経由した輸出規制品の取引にもつながったのでしょう。
本書のタイトルは、サプライチェーンを止めることの比喩ですが、イランの核開発、ロシアのクリミア侵攻、中国の技術覇権、ロシアのウクライナ侵攻という出来事に対して、該当国に武力を使わずに対抗する手段として経済制裁が用いられ、その時の当事者たちの対応が記されています。
本書で記している制裁は、紛争や軍事的な脅威に対して軍事力を行使していません。経済的な影響力を行使することで、該当国を制止することを意図しています。読者は、本書に挙げられた5つの出来事を通して、為政者の意思決定の相互作用で作られる現代史と、経済面でのUSドルの影響力を把握することになるでしょう。
中国の5Gネットワークを巡る経緯には、評者が本書を読んで始めた知ったことも含まれていました。また、ロシアのウクライナを巡る行動は、何人もの過去の歴史上の人物を想起させます。クリミア侵攻から"Novorossiya"(New Russia)という思想に取り憑かれた権力者が、周囲のスタッフが立案したプランを実行する様は、100年前にも、200年前にもあった光景と重なります。
ミンスク合意では、2015年末までに、東側の国境をキエフの統治下に返すことをモスクワに要求していました。ロシア指導層の"Novorossiya"ファンタジーは、ウクライナへの侵攻という形で現在も継続しています。ヘルソン、ドネツク、ルハンスク、ドンバス、クリミアはロシアが占有しています。
合衆国政府が仲介を試みた最近の停戦への交渉後に、それがどういう経路を辿るか不確実ですが、彼らが保持するファンタジーは放棄されません。つまり、次に彼らの当初のプランに含まれていたモルドバが脅威に晒されます。そして、彼らの幻想はバルト三国に向かうかもしれません。現在の指導層と主流派の知識人が見ているユーラシア・ユニオンは"Novorossiya"が中心にあります。そしてモルドバの東側の分離独立派は、ロシアへ併合される望みを抱いています。
EUを意識したユーラシア・ユニオンとその中心にある”Novorossiya"という思想は、現在のロシアの指導者が退場した後も残るであろう概念です。それはロシアによる欧州の国境線が変わるリスクが存続することを意味します。
こうした考えや思想は、事実に関わらず論理的にも倫理的にも錯誤の上で成立し、継承されていきます。これは信仰の特徴でもあります。日本では、錯誤の上で成立している外為市場介入が、この類の例に挙げることができます。日本の外為市場介入は、時代や環境、担当者が変わっても繰り返し実施されています。
経済制裁は、USドルの影響力を行使したものです。現在の合衆国の政策として関税やレアメタルの調達先、多角化の動きは、サプライチェーンの再構築によって、特定の国に対する経済的な依存を無くしたいことの現れでしょう。地政学的な問題の上昇によって、安価な調達先に恵まれた経済のグロバリゼーションの減速に、いくつかのブロック経済圏に向かう流れが生じています。
思想、信条で世界が様変わりし、歴史が作られてきたことを考えると、民主主義という考えがポピュリズムに影響されようとも、政治システムとして存続し続ける必要があることを再認識することになります。その民主主義にも色々あるようですが、現代の専制的な政治システムの詳細な実像とその経済の特徴、マクロな影響は、別の機会に記しましょう。